こんにちは、鹿児島市の〈ピアノ・声楽教室〉かごしま音楽教室Sing!の郷田です!
よく、イタリアの発声法は「ベルカント唱法ですよ」という言葉を聞きます。実は「ベルカント」という言葉(bel canto)は、「良い歌」という意味で、「ベルカント唱法」というのは「良い歌を歌う方法」くらいの意味なんです。企業秘密的な、特別な…そんな言葉ではないんですね。
私が留学していた20年前頃はですが、各先生によって発声の指導法はそれぞれでした。しかし、おおよそ2つのメソードに仕分けることができるのではないかなと思います。この2つは、太陽と月くらい全く違う物です。
一つは、1800年代前半までの歌い方、もう一つは1800年代後半からの歌い方です。その1800年中盤頃にどんなことが起こったのか。それは、
テノール歌手の発声で、革新的な出来事があったことに由来します。ジルベール・デュプレ、というテノール歌手の出現でした。それまで、ファルセットーネ(高い音を頭声で出す)が主流だった高音の出し方でしたが、このデュプレさんは「胸声で」ハイC(テノールの最高音)を出したのです。その当時の聴衆は度肝を抜かれたそうです。デュプレのライバルテノールの中には、デュプレがこの声で歌い出したことがきっかけて自殺をした人もいたとされています。
このデュプレの出現がそうさせたのかまでは定かではありませんが、いずれにせよこの後のイタリアオペラは、甘美な旋律重視の音楽からドラマティックな強い声を求められる時代になりました。ヴェルディのオペラがまさにそうで、そしてそれ以降も「ヴェリズモオペラ」という激情的な作品が次々に作られていきます。歌手もデュプレの出現以降、テノールに限らず、皆が「強い声」で歌う時代へと変化していきます。
ヴェリズモ時代にこの「強い声」を保つ発声法を確立したのが「エンリコ・カルーソー」というテノールでした。
1800年代以前の発声法とそれ以降とでは、特に「横隔膜の扱い方」「喉頭の扱い方」においてかなりの差異があります。1800年代以前は、横隔膜や喉頭が「高い位置」にポジションを取るのに対して、ヴェルディ以降ヴェリズモの発声法では「低い位置に保たれる」ということをトライしていくメソッドです。
伝統的なベルカント唱法、というと実は前者の方で、そのメソードで教える先生も私が留学した頃にはいらしたと思います。ドラマティックな声を目指すためには後者のメソッドに傾倒する必要があり、それは逆に「フィジカル(体の力)」を必要とするために、習得に時間がかかり、アスリート的な思考も必要になってくるものです。
ということで、正しい発声法は一つではありません。自分が目指す歌と、その発声法が一致している必要があるので、先生を探している方はその辺も理解して、自分に合った指導者かどうかを検討する必要があるかもしれません。

GOUDA AKITOMO(音楽家、作業療法士)
武蔵野音楽大学卒業、同大学院修了。イタリア国立ボローニャ音楽院留学。2004年「第35回イタリア声楽コンコルソ」ミラノ大賞、松下電器賞。2007年「第12回世界オペラコンクール新しい声」アジア予選ファイナリスト。発声法の研究のために解剖書を読み漁ったことからリハビリに興味を持ち、身体や脳の機能など専門教育を経て作業療法士の国家資格を取得。かごしま音楽教室Sing代表。
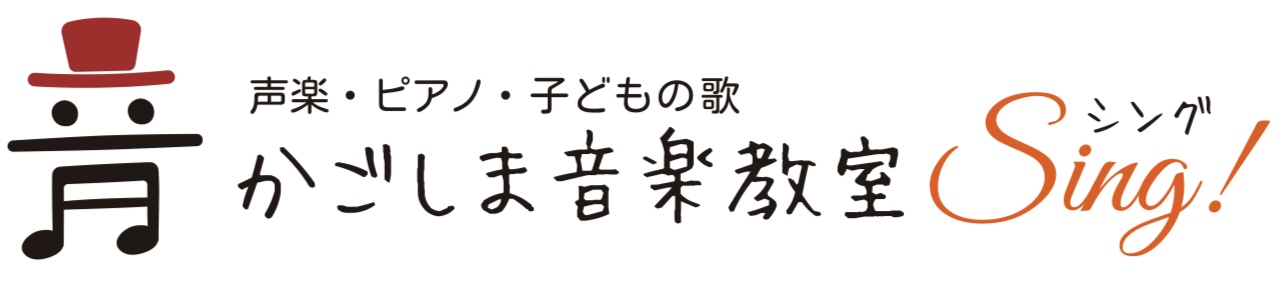

コメント